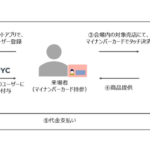工場の生産ラインなどで使用される産業用ロボット。産業用ロボットの効率を最大限に上げるうえでは、ロボットハンドが重要です。
そこで本記事では、ロボットハンドの種類や選ぶ際の注意点、活用事例を紹介します。また導入事例の解説を通じて、失敗しないロボットハンドの導入方法が理解できるでしょう。
ロボットハンドの導入を検討中の企業の皆さまは、参考として活用ください。
目次
ロボットハンドとは
ロボットハンドとは、主に産業用ロボットの先端に付属する、人間の手や指の役割を担う部品を指します。生産性や品質向上を図るために、対象物を掴む・持ち上げる・運ぶ・支えるといった人間が手を使って行う動作を機械が代わりに行ってくれるものです。
人間の手と同様の5本指や2・3本指など、さまざまな指の本数のロボットハンドが提供されています。
ロボットハンドの種類
ロボットハンドには種類があり、把持ハンドと吸着ハンドの2つに分けられます。
さらに、把持ハンドは電動型と空気圧型、吸着ハンドは真空型と磁力型に細かく分類されます。適正なロボットハンドを選定する際の基準は、使用する場所や用途によって異なるのです。
以下で詳しく解説しますので、確認しましょう。
把持ハンド
把持ハンドとは、人間の指のように、挟んで持つタイプのロボットハンドのことです。指の数は、2本のものや4本のものがあります。人間の指のようにさまざまな形状・素材の対象物を挟んで持てます。
また、把持ハンドは内蔵された力学センサーにより敏感に圧力を検知できるため、繊細な動きが可能です。そのためデリケートな対象物や、強い圧力を要する対象物の把持シーンでも活躍します。
把持ハンドは、駆動力によって電動型と空気圧型に分かれます。
電動型
電動型ロボットハンドは、電力を駆動源としてチャックを作動させるタイプのものです。
電動ならではの位置・速度の制御機能を活かして、動作中に対象物を掴む際の位置を自由に設定できます。したがって、対象物のサイズや向きが不揃いである場合でも把持が可能です。
電動型ロボットハンドは、空気圧型に必要なエア供給用のホースやコンプレッサが不要なので、比較的シンプルに接続できます。
空気圧型
空気圧型ロボットハンドは、空気圧を使って指の背面を膨らませて指を曲げるタイプです。高度な機構がないため、比較的シンプルな設計です。
空気圧型ロボットハンドは安価な価格帯で提供されているため、消耗時には低コストで指ごと交換できるメリットがあります。
また空気圧型のロボットハンドは、ロボットハンド自体の重量を抑えられるため、装備が重厚になりがちな電動型と比較してメリットといえるでしょう。
吸着ハンド
吸着ハンドとは、対象物を吸着して運ぶタイプのロボットハンドのことです。把持ハンドのように挟んで持つ動きがないため、素早く掴んで離す工程に向いており、かつ比較的軽量な対象物を運ぶのに適しています。
また吸着部が汚れると、吸着力が弱くなってしまう特徴があります。吸着力が弱まると対象物が落下してしまうリスクがあるため、こまめなメンテナンスが必要です。
吸着ハンドは、どのように対象物を吸着させるかによって真空型と磁力型に分かれます。
真空型
真空型ロボットハンドは、真空発生器により発生させた真空を利用して、先端の真空パッドに対象物を吸着させて運ぶタイプです。真空状態を作って吸着するため、対象物の表面に凸凹や穴があったり、水や油などが付着したりしていると吸着が安定しません。
真空発生器やエアコンプレッサなどの設備が必要なため、初期設定にかかる負担が大きくなる傾向があります。
磁力型
磁力型ロボットハンドは、電磁石のオンオフによって対象物を吸着させるタイプです。
電磁石のため、表面に凸凹や穴がある対象物や、表面に小さな穴が多数空いている多孔質の金網や、鉄製スポンジなどの把持シーンで利用できます。一方で、磁力に反応しない非鉄金属は、吸着できないため利用できません。
磁力型ロボットハンドのメリットとしては、省電力で強力な吸着力を発揮できる点が挙げられます。
ロボットハンドの機構に関しては下記記事をご覧ください。
ロボットハンドの機構ロボットハンドの機構とは?設計や特徴・選び方まで解説
ロボットハンドを選ぶ際の注意点
ロボットハンドにはさまざまな種類があります。そのため、取り扱う対象物や用途・目的に見合ったロボットハンドを選ばないと、生産性や効率性が落ちてしまいます。
そこで、ロボットハンドを選ぶ際の注意点を紹介します。
把持・吸着力は適正なのか
対象物を把持したり吸着させたりするロボットハンドの機能から、対象物の重量に合わせてロボットハンドを選ぶ必要があります。
対象物の重量に耐えられないロボットハンドを選んだ場合には、対象物を落とし、破損させてしまう事故にもつながりかねません。そのためロボットハンドが、対象物の重量を把持・吸着できるかどうかを見定める必要があります。
特に共通のロボットハンドで複数作業を行う場合には、対象物の重量が異なる場合もあるので、十分取り扱いに注意しましょう。
ロボットハンドの材質が対象物と合っているか
ロボットハンドを選ぶ際には、材質が対象物と合っているかどうかも確認しましょう。
例えば、対象物の表面に多数の穴が空いてる場合は、真空状態が作れないため、真空型のロボットハンドは利用できません。
また、水や油で表面が濡れている対象物の場合は、把持ハンドで掴もうとしても滑り落ちてしまう恐れがあります。柔らかくて崩れやすい対象物には、把持力が強いロボットハンドは適しません。
ロボットハンドの制御精度を確認
ロボットハンドの動作の制御精度も、重要な選定ポイントです。ロボットハンドを制御する際には、カメラを使って製品の位置を把握したり、力学センサーによって力加減を調整したりします。
ロボットハンドに搭載される各種センサーやモーターなどの制御機器の種類によって、位置決めの精度が大きく変わります。特に、小さい製品を扱うなど細かい作業になればなるほど、高精度な位置決めが可能なロボットハンドが必要です。
信頼できるロボットハンドなのか
ロボットハンドを利用する場面は、長時間連続で稼働させる場合が多いため、大きな負荷がかかります。したがって、ロボットハンドの耐久性や耐用年数は選ぶときの重要なポイントです。検討中のロボットハンドメーカーが信頼できるか、十分に確認しましょう。
またロボットハンド導入後の保守・メンテナンスなど、ランニングコストに見合ったアフターサービスがきちんと整備されているかどうかも重要なポイントです。
ロボットハンドの活用事例
次に、これまで述べてきたさまざまな種類のロボットハンドが、工場などでどのように活用されているのか、具体的な活用事例を5つ紹介します。
崩れやすい食品のピッキング
ロボットハンドは、やわらかくて形が崩れやすい対象物のピッキングで活用が進められています。
有限会社福田屋製菓では人手不足や衛生管理面からロボットの導入が求められていましたが、バウムクーヘンがつぶれやすく通常のロボットハンドでは把持しにくい点が課題でした。
そこで、ニッタ株式会社製のロボットハンド「SOFTmatics」をバウムクーヘンの製造工程に導入しました。SOFTmaticsはウレタン樹脂であるため、不定形でつぶれやすい製品でも、やさしく掴めるロボットハンドです。独自の把持機構で滑らかな動きが可能なため、バウムクーヘンでもソフトに掴めるのです。
導入前のロボットハンドでは3パーセント程度は落としていましたが、SOFTmaticsを導入後は3,600個のバウムクーヘンをすべて落とさずにピッキングできるようになりました。
袋物製品のハンドリング
ロボットハンドは、袋物製品のハンドリングでも活用されています。
例えば、ある食品業界の箱詰め工程では、川崎重工製のロボットに真空グリッパーを装着し、コンベア上にある袋物製品のハンドリングから箱詰めに使われています。ロボットハンド導入により、袋入り食品の箱詰め工程の自動化に成功しました。
導入したロボットハンドでは、コンベアを流れてくる袋を川崎重工のビジョンシステム「K-VFinder」が認識しカメラで撮影します。そして、ビジョンシステムのデータをコンベアトラッキングデータとともにロボットに送り、袋をピッキングする位置を正確に決定します。
これにより、毎分80袋を箱詰めが可能となり、製品が落下するトラブルも発生していません。
高温部品のトリミング
ロボットハンドは、高温部品のトリミング工程のような過酷な環境でも積極的に活用されています。
例えば、那須工業株式会社は、溶かした金属の成形製品であるアルミダイカスト部品のトリミング工程にロボットハンドを導入しています。従来トリミング工程は、溶融炉のそばで高温の破片が飛び散るリスクがあるような危険な作業環境下で行われていたため、改善が急務でした。
そこで熱と振動に強いロボットハンドを導入し、トリミング作業の自動化と作業環境の改善に成功しました。ロボットハンドの導入により、従業員のやけどや熱中症のリスクを削減できています。
組み立て作業
ロボットハンドは、高温部品のトリミングなどの組み立て工程にも導入されています。
例えば、カナエ工業株式会社では、AT車を構成するトルクコンバーターのブレードの組み立て工程にロボットハンドを導入しています。従来は作業者が手作業でブレードをハンマーで打ち込む作業を行っていましたが、作業者の経験知によるところが大きく、完成品の品質が不安定でした。
そこで品質の向上を目指して、作業者の経験知を機械的に再現するロボットハンドを導入。ロボットハンドなどの導入により、生産性の向上が図れたとともに、作業者の熟練度に左右されていた製品の品質の安定化に成功しました。
パレット積み作業
ロボットハンドは、パレット積み作業でも活躍しています。
株式会社シンセイ福岡では、化粧ブロックの積み作業工程にロボットハンドを導入しました。しかし、重く壊れやすい化粧ブロックを慎重に取り扱いながら積む作業は、作業者に過酷な労働を強いていたため、生産性が低くなる点が課題だったのです。
そこで、重くて壊れやすいブロックでも搬送できるよう、割れ欠けを低減するロボットハンドを導入しました。
ロボットハンドは、異なるサイズの化粧ブロックでも瞬時に大きさを検知し、崩れないように把持力も適度となっています。さらに落下防止機能も備えているため、重労働や危険な作業から作業者を解放し、高速化と生産性向上が実現できました。
ロボットハンドメーカーに関しては下記記事をご覧ください。
ロボットハンドメーカーロボットハンドメーカー25選!導入事例や選ぶ際の注意点
ロボットハンドの導入方法
ロボットハンドの導入方法はさまざまですが、ロボットSIerに頼ると効率よく導入可能です。ロボットSIerを利用すれば、産業用ロボットや適切なロボットハンドの導入を提案したり、組み立てを行ったりしてくれます。
参照ロボットSIer(ロボットシステムインテグレータ)とは?導入事例や補助金・おすすめメーカー5選まで
「ロボファン」では、数あるロボットSIerのなかから、各企業に最適なロボットSIerを紹介します。ロボファンで紹介しているロボットSIerでは、現場視察に基づいた導入計画の判断や作業の選定、導入レイアウト図の作成など、初期段階で導入診断をしっかりと行います。そのうえ、導入後のアフターサポートもあるので、安心してロボットハンドを導入できます。
プロに任せて適切なロボットハンドを導入し、自動化と効率化を実現しましょう。
まとめ
ロボットハンドには、把持型や吸着型など、さまざまな用途・作業環境に対応したものがあります。そのため、導入を検討している企業の皆さまは、どのような機能を持つロボットハンドを採用すべきか迷われるかもしれません。
そこで、紹介したロボットハンドに関する基礎知識や選ぶときの注意点、導入方法が参考になります。自社工場や開発現場などの生産性向上・品質の安定化のためにロボットハンドの導入をしましょう。
どのようなロボットハンドを導入すべきか迷ったら、ぜひロボファンへお問い合わせください。