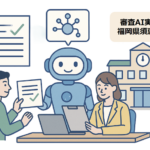2015年6月に発売されたSoftbankのPepperを皮切りに、ここ日本でもロボットへの関心の高まりが感じられるようになってきました。
ところで、一口に「ロボット」と言っても実際には様々なタイプがあるのをご存じでしょうか?
前述のPepperのように感情を理解し、人と対話するようなものもあれば、工場などで活躍する産業用ロボット、あるいは軍事用ロボットなども存在します。
この記事では、今後日本において発生が懸念される巨大地震において活躍が期待されている「レスキューロボット」について解説します。
レスキューロボットとは?
レスキューロボット(Rescue Robot)とは、その名のとおり、救難救助を目的として設計されたロボットです。
地震や水害などの災害、あるいは遭難などの危機から人間を救助する目的で作られるロボットを総称して、レスキューロボット、あるいは救助ロボットと呼びます。
※災害対応を専門として作られているものは「災害対応ロボット」と呼ばれることもある。
地震などの災害でビルや家屋が倒壊し、瓦礫が散乱すると、被災者を発見するのが著しく困難となります。
また、被災者がそこに居ることが分かっていても、何らかの危険により人間が救助に向かえない場合もあるでしょう。
こうした場面で、人間に変わって災害現場の状況調査や被災者の救助を行う、レスキューロボットが活躍するのです。
レスキューロボットの歴史
日本におけるレスキューロボット研究の歴史は比較的浅く、研究が活発化し始めたのは、1995年に発生した阪神・淡路大地震以降です。
まず、1996年に「救助ロボット機器の研究開発に資することを目的とした阪神淡路大震災における人命救助の実態調査研究会(レスキューロボット機器研究会)」による調査研究が開始されました。
しかし、本格的な研究開発に着手されたのは、2002年に始まった「文部科学省大都市大震災軽減化特別プロジェクト」(大大特)からだと言われています。
その後、2011年に発生した東日本大震災をきっかけとして、レスキューロボットに対する関心がにわかに高まり、従来行われていた研究・開発が活発化したと言われています。
レスキューロボットのタイプ
レスキューロボットは、大きく二種類に分類することができます。
- 災害現場の情報収集や要救援者の探索を行うタイプ
- 瓦礫の撤去などを行う建設重機のようなタイプ
2016年現在では、倒壊した建物や危険な区域における人の探索を目的としたレスキューロボットの開発に、特に注目が集まっているようです。
このような探索用ロボットは、倒壊した家屋や瓦礫などが散乱する悪路を難なく乗り越えていける走行性能を備え、ビデオやカメラ、あるいは周囲の状況を計測するためのセンサ類を搭載して、対象エリアの情報収集を行います。
現時点ではレスキュー隊員がリモートコントローラーで操作するリモコンタイプが主流ですが、将来的には自律的に動作するものがメインになっていくと考えられています。
災害対応ロボット「Quince」の活躍

Quince
探索用レスキューロボットとして有名なのは、東北大学の田所研究室が開発する災害対応ロボット「Quince(クインス)」でしょう。
Quinceは、福島第一原発事故現場において、原子炉建屋内の放射線量測定や写真撮影、ダストサンプルの採取を行い、海外各国でも話題を呼びました。
また、災害で閉鎖した地下街や半倒壊した建物を調査し、情報収集を行うことができます。
Quince自体が救助活動を行うわけではないものの、Quinceが収集した情報を活用することで、救助活動を円滑に行うことが可能となります。
いわば、救助活動の有能なアシスタントというところでしょうか。
レスキューロボットは地震大国日本の救世主となるか!?
地震大国日本において、近い将来発生が懸念される南海トラフ巨大地震などに備えるために、日本国内の様々な研究機関でレスキューロボットの研究が進められています。
近年、IoT、ビッグデータ解析、人工知能といったテクノロジーが目覚ましい発展を遂げつつありますが、こうしたテクノロジーを取り込みながら、レスキューロボットは今後もますます発展していくことでしょう。
前述のQuinceを初めとして、今後も様々なタイプのレスキューロボットが開発され、災害時の救助活動を手助けしてくれることを期待したいですね。
<参考サイト>