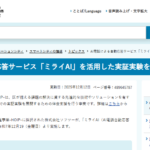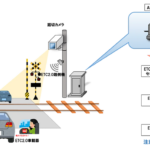現在、飲食業界で話題の配膳ロボット。配膳ロボットとは、商品をロボットに乗せ目的のテーブルまで届けるなど、配膳の自動化を可能にしたロボットです。
配膳ロボットを導入すると、業務の効率化が図れ、人手不足を解消できるだけでなく、お客さまの満足度向上を期待できます。しかし、配膳ロボットの仕組みが分からないため、安全面で不安を感じている方も多いでしょう。
そこで本記事では、配膳ロボットの仕組みについて詳しく紹介します。この記事を通して、配膳ロボットの最新技術も知ることができます。安全性や利便性を実現したいと考えている飲食店のオーナーの皆様は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
配膳ロボットとは
配膳ロボットとは、人に代わって配膳業務を行うロボットです。人が行ってきた配膳業務をロボットが担うことで、コスト削減や業務効率の改善が期待できます。
配膳ロボットが人や物にぶつからない仕組み

ここでは、配膳ロボットの7つの仕組みについて紹介します。
- 人や物にぶつからない【3D障害物回避センサー】
- 目印になるタグを設置する【タグナビゲーション式】
- 位置の特定と環境地図の作成を同時にする【SLAM】
- 複数台チームワーク【PUDUSCHEDULER】
- お店やメニューの宣伝をする【広告スクリーン】
- お客さまへ自ら挨拶をする【AI音声技術】
- 手をかざすことで移動の合図ができる【ヘッドセンサー】
人や物にぶつからない【3D障害物回避センサー】
3D障害物回避センサーとは、障害物などの幅や高さ、形状を立体的に検出し、人や物体との衝突を回避できる仕組みです。ロボットに搭載された3Dカメラや赤外線センサーにより周囲を常に監視し、進行に合わせて位置補正を行います。
例えば「BellaBot」は3D障害物回避機能により、上下左右幅広い領域の障害物の位置を的確に認識できるため、安全に移動できます。回避センサーがある配膳ロボットは、人やイスなどの障害物を検知すると適切な回避行動を選択できるため、安全にお客さまの席まで配膳を行えるのです。
目印になるタグを設置する【タグナビゲーション式】
タグナビゲーション式とは、目印となるタグを店内に設置して配膳ロボットの移動制御方式です。
天井のマーカーをロボット上部の赤外線センサーが読み取ることで、ロボットが動く仕組みです。センサーにより読み取りを行う都合上、高さが4メートル以内のフラットな形状の天井での利用が推奨されています。配膳ロボットの「PEANUT」では赤外線センサーによるタグナビゲーション式により、配膳の度に進路を指定する必要がなく、効率的な配膳を実現しています。
位置の特定と環境地図の作成を同時にする【SLAM】
SLAMとは、「自己位置の推定」と「店内の地図作成」を同時に行う仕組みです。センサーで店内のテーブルや椅子などの位置を環境地図として構築し、配膳ロボットの移動量を推測します。
SLAMにより、配膳ロボットは人間の補助なく、ガイドなしでの自律的な配膳を実現できます。そのため、SLAM技術を搭載した「Keenbot T8」では、自動的に位置決めを行い、あらゆる環境で自律した走行が可能です。
また、内装工事が必要ないため、店内の景観を損なわずに利用できるのもメリットの一つです。
複数台チームワーク【PUDUSCHEDULER】
PUDUSCHEDULERとは、分散型の柔軟なアドホックネットワーク通信方式を使ったPudu製ロボット独自の制御方法です。Pudu製の「KettyBot」では、ユーザ側の操作を必要とせずロボット同士が直接通信できるため、複数台の配膳ロボットが互いのタスク内容や移動量を調整しながら作業を分担できます。
人間のスタッフ間でかけ声をしながらホール業務を分担するように、同一ネットワーク内のロボット同士で通信し最適な行動を取ります。
お店やメニューの宣伝をする【広告スクリーン】
広告スクリーンとは、ロボットの前面に設置されたディスプレイにより、配膳しながらお店やメニューの宣伝ができる仕組みです。例えば「Lanky Porter」では、頭部のスクリーン上で映像やテキスト画像の表示が可能で、店舗の特典やおすすめメニューなどの情報を視覚的に紹介できます。
広告スクリーンを通じてお客さまにとって魅力的な情報を伝えられるため、購買意欲を高められると同時に売上アップが期待できるでしょう。。
お客さまへ自ら挨拶をする【AI音声技術】
AI音声技術とは、AIの自然言語処理アルゴリズムにより、配膳ロボットが自らお客さまの言葉を自動で解釈して自己紹介や挨拶ができる技術です。例えば、「Servi」では「おすすめの商品はこちらです」など、お客さまの質問に対して適切に回答できます。
AI音声技術により、単なる運搬ロボットではなく、対人コミュニケーションも可能な接客ロボットとしての役割も担えます。
手をかざすことで移動の合図ができる【ヘッドセンサー】
ヘッドセンサーとは、ロボットの頭部に設置された赤外線センサーに手をかざすと移動の合図ができる仕組みです。お客さまは手をかざすことで、ロボットに対して目的地や動作の指示を行えます。例えば「Holabot」は、ヘッドセンサーで手の動きやジェスチャーを検知し、自動的に別のテーブルへ移動を開始できます。
また、直接画面をタップしなくて済むため、衛生的でお手入れも簡単です。
配膳ロボットの活用シーン
以下の場面で、配膳ロボットの活用が進んでいます。
- 飲食店での配膳下げ膳業務
- 物流倉庫でのピッキング作業
- 医療現場での備品の運搬
配膳ロボットが普及している理由
配膳ロボットの普及が進んでいる主な理由として、人手不足が挙げられます。特に飲食業界では慢性的な人手不足で、1人あたりの業務量が増えてしまう傾向にあります。
そこで、人と同じもしくはそれ以上に効率よく配膳ができる「配膳ロボット」が普及しているのです。
まとめ
今回は、配膳ロボットの仕組みについて解説しました。配膳ロボットは「LiDER」と呼ばれる技術を使って、対象物の距離や性質を特定し、衝突を避けながら運搬できます。
また、配膳ロボットを導入している業界は、飲食業界や医療業界など、さまざまです。飲食物の配膳に限らず、医療現場における備品の運搬にも活用されていることから、利用する業界は今後増えていくでしょう。
人手不足や業務の効率化に悩んでいる方は、この機会に配膳ロボットの導入を検討しましょう。